阿蒙、阿瞞、阿斗、阿鴦、阿多、阿黙、阿蘇、阿童、白鶴、鷂鴟、万億といったこれらの幼名はどの三国志武将のものなのか。
呉下の阿蒙

「呉下の阿蒙」って言葉あるでしょ?

呂蒙でしたっけ?

そう、呂蒙の幼名。「阿」には「~ちゃん」という意味があるみたいね。
かつて無学で粗暴だった呂蒙が孫権に諭されて猛勉強し智勇兼備の名将となったと。
そんな変貌をとげた呂蒙に魯粛が「呉下の阿蒙にあらず」といったと。

蔣欽も勉強したんですよね。
しかし、いい言葉ですね。

いい言葉なのよ。
ただ、「呉下の阿蒙」って言葉単体だと、無学な人、進歩しない人って意味なんだよ。
なんかひどくない?
そんな言われ方するほど昔の呂蒙ってひどいの?

たしかに呂蒙って言ったら、三国志の中でも屈指の名将ですもんね。

「呉下の阿蒙」って言葉より、先に呂蒙を知ったから、この言葉にすごい違和感あるんだよ。
なんだか、よっぽどのエピソードがないと納得できない。

たしかに!
じゃあ、アイツに「呉下の阿蒙」の由来を聞いてみたらどうですか?

アイツかあ。
聞いてみよう。
「呉下の阿蒙」とは、中国の春秋時代に生きた阿蒙という人物が、呉王阖闾に出会い、その才能を認められて重用されたという故事に由来しています。
阿蒙は、春秋時代の晋国で生まれました。彼は若い頃から非常に才能があり、学問や兵法、音楽などあらゆる分野に秀でていました。ある日、阿蒙は晋国を離れ、南方の呉国に移り住みました。そこで彼は呉王阖闾に出会い、その才能を認められて重用され、国の重要な役職に就くこととなりました。阿蒙は呉国の発展に多大な貢献をし、その名声は後世にまで残りました。
この故事は、後に『呉下の阿蒙』という諺(ことわざ)になり、「適材適所に置くことが重要である」という意味で使われるようになりました。また、『呉下の阿蒙』という言葉は、能力を持った人材が、正しい環境で育まれ、才能を発揮できるようになることを表すこともあります。
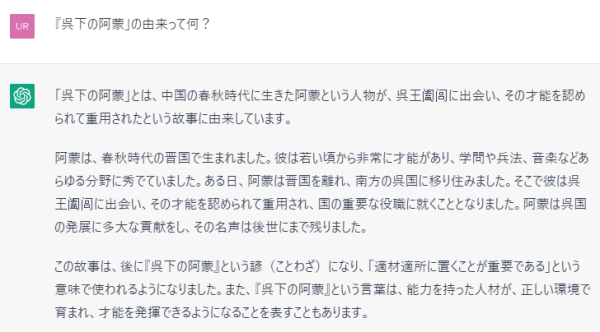

なんか勝手なこと言っとる!
阿蒙が幼名じゃなくて名前になってるし、時代も三国じゃなくて春秋だ!

阿蒙だけで『呂蒙』の名は全く出てこないですね。
この呉王の名前なんですか!?見たことない漢字!

たぶん春秋五覇の一人、呉王の闔閭(こうりょ)。
あの孫子こと孫武や、元祖「死者に鞭打つ」の伍子胥(ごししょ)の王様だ。

実在の人か!
春秋五覇のあと四人は誰なんです?

あと十人ぐらい候補がいるからよくわからん。
ただ、斉の桓公と晋の文公は絶対。桓公は「管鮑の交わり」の管仲と鮑叔が仕えた人だ。

てことは十二人!!!春秋五覇つってんのに!?
五人いる龍造寺四天王がかわいくみえますね。

昔の人が勝手に”僕の考える最強の春秋五覇”をやっちゃったんだろうね。

で、その闔閭が阿蒙を重く用いたことから、『呉下の阿蒙』が「適材適所に置くことが重要である」という意味になったと。

て、ChatGPTが勝手に言ってるだけですよね。

勝手に言ってるだけ!
もっともらしいけどめちゃくちゃだよ。
呉下の阿瞞

三国志の幼名で言えば、阿瞞も有名だよね?

曹操だ!蒼天航路で知りましたよ!


『呉下の阿瞞』の由来を聞いてみようか?

そんな言葉もあるの?

いや、ないよ。
ないけどアイツなら、適当な由来を作りそうでしょ。聞いてみよう!
「呉下の阿瞞」とは、三国時代の呉の武将・孫権が、蜀の武将・諸葛亮に対して使った蔑称です。
孫権は、諸葛亮が率いる蜀軍に敗れた後、彼の作戦や才能を軽視して、彼を「阿瞞」と呼びました。これは、諸葛亮が裏切り者や偽者であるという意味を含んでいるとされています。
しかし、後に孫権は自分の誤りを認め、諸葛亮の才能を再評価することになりました。そのため、「呉下の阿瞞」という言葉は、後世には「自分の偏見や誤解によって、優れた才能を見抜けなかった人物」という意味で使われるようになりました。また、諸葛亮自身が「阿瞞」と呼ばれたことから、あるいは他人に自分自身を過小評価されたことを嘆く際に使われることもあります。
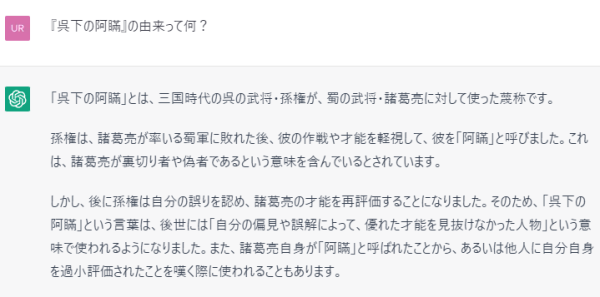

孫権が孔明に使った蔑称!!!

しかも孔明に負けた時に放ったという負け惜しみの言葉、
それが『阿瞞』!

でも、後に孫権は孔明の才能を認めたんですね。

それで『呉下の阿瞞』は、才能を見抜けなかったという意味と、過小評価されたという意味があると。

孫権の扱いですね。

そして、全く登場しなかった曹操。
呉下の阿斗

他に有名な幼名といえば、『阿斗』があるね。

アホの劉禅!

長坂橋の時に劉備が地面に叩きつけられたからアホになった説あるよね。

あれって本当に叩きつけたんですか?演義の演出ですよね?

だと思うけど、
でも、あの時代の人ってイカれてるからやっててもおかしくないよ。
特に劉備なんてイカれてるし!

劉備ってイカれてるんですか?

劉備はイカれてるよ!
黄巾の乱の後に、地方の役人になったでしょ?あの時のエピソードいかれてるよ。
郡の督郵が公の仕事で来たとき、先主は面会を求めたが、許されなかったので、すぐさま押し入って督郵を縛りあげ、二百回も杖でうちすえ、自分の官印の綬をはずして彼の頸にひっかけ、馬つなぎの柱にくくりつけると、官職を棄て逃亡した。

この先主が劉備ね。
要は、職場に本社や本部から監察官が来たんだよ。その人に面会を断られただけでコレよ。
こんな仕事の辞め方ある?

狂ってま回すね!!!
二百回多いし。

二百回は結構時間かかるよ。普通はその間に怒りも冷めるでしょ?
関羽と張飛もその間ずっと待ってるよ?

また始まったって感じなんでしょうね。

そう!
だから劉禅があぁなっちゃったのはしょうがないのよ。
てなわけで、『呉下の阿斗』を聞いてみよう!
「呉下の阿斗」という言葉は、三国時代の蜀漢の皇帝劉禅(りゅうせん)の幼名であり、蜀漢滅亡後に彼が漢中王として生活していた時期を指すことが一般的です。
劉禅は、蜀漢の創始者である劉備の子であり、彼が亡くなった後に後継者として即位しました。しかし、劉禅は非常に臆病な性格で、政治の実権を握ることができず、重臣たちによって操られることが多かったため、周囲から軽蔑されることがありました。
その後、蜀漢が滅亡すると、劉禅は漢中に移され、漢中王として生活しました。この時期の劉禅は、周囲から「呉下の阿斗」と揶揄されることが多かったと言われています。この「呉下の阿斗」という言葉は、劉禅が非力で、周囲に操られているような印象を与えることから、後世に「才能があるのに、その才能を生かしきれない人物」を指す表現として用いられるようになりました。
また、劉禅が幼名として持っていた「阿斗」という名前は、彼の臆病な性格や軽薄な印象を表すような意味合いもあるため、後世にも「阿斗」という言葉は、軽薄で無力な人物を表す表現として使われることがあります。
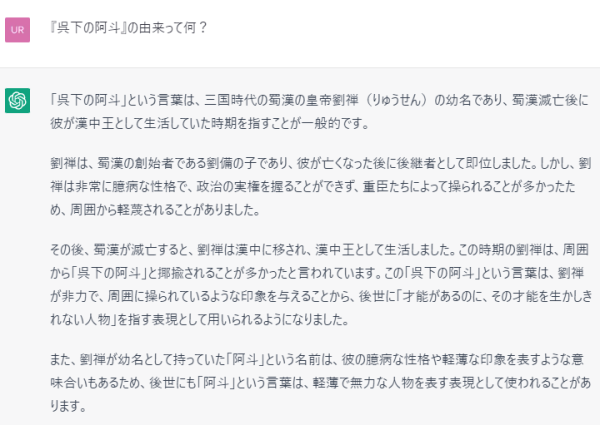

ちゃんと”蜀漢の皇帝劉禅の幼名”って言ってますね。
で、劉禅が非常に臆病な性格だから、「阿斗」という言葉は軽薄で無力な人物を表す表現になったと。

実際、「阿斗」は中国では無能って意味らしいからね。

なるほど。
「阿斗」は言葉として実際にあるから、あまり外れてないんですね。

何年経ってもひどい言われようだけどね。
もう許してあげればいいのに。

でも、ChatGPTによると、
『呉下の阿斗』は「才能があるのに、その才能を生かしきれない人物」って意味らしいですよ!

是非とも、この言葉が広まって劉禅の名誉が回復されてほしいよ。

そうですね。
ただ、劉禅は呉じゃないから無理でしょうね。

そうだね。
呉下の阿鴦

じゃあ、この幼名わかる?
『阿鴦』。

阿鴦?

ヒントはガチムチ系。

武安国!

武安国はムチがちょっと強いかな。

正解は、毌丘倹の乱や諸葛誕の乱で活躍した文鴦。

後半の魏の武将ですね。

演義では趙雲に匹敵するとされた文鴦。
元の名は俶で、鴦は幼名。

大人になっても幼名で呼ばれてたんですね。

卓球の福原愛さんだって、いつまでたっても「愛ちゃん、愛ちゃん」言われてたでしょ。

そうでしたね。
でも、さすがに最近「愛ちゃん」って呼びづらいですけどね。

いろいろあったしね。
もう『呉下の阿愛』とは呼べないな。

阿愛!!!しかも呉!

さて、では『呉下の阿鴦』で聞いてみようか。
「呉下の阿鴦」という言葉は、三国時代の呉の女性・小喬(しょうきょう)のことを指します。
小喬は、呉の初代皇帝・孫堅の娘で、美しさで有名でした。彼女は、劉備が蜀漢を建国する際に、劉備の妻・甘夫人として嫁いでいましたが、その後、劉備との間に子供をもうけることなく亡くなりました。
「呉下の阿鴦」という言葉は、小喬が呉の宮廷にいた頃、周囲から「鴛鴦」と呼ばれていたことに由来しています。鴛鴦は、オスとメスの鳥が常にペアでいることから、男女が深い愛情で結ばれていることを表す象徴とされています。小喬が「鴛鴦」と呼ばれたのは、その美しさと、彼女が孫権と深い愛情で結ばれていたとされることからきています。
しかし、小喬が亡くなった後、彼女を慕っていた男たちは、彼女が「阿鴦」と呼ばれるようになりました。この「阿鴦」という言葉は、小喬が亡くなった後、彼女を慕って彼女に扮する女性が多く現れたことに由来しています。彼女たちは、小喬の代わりとして、男たちを癒やす存在として扱われ、後に「阿鴦」という言葉は、「男たちを癒やす女性」という意味で使われるようになりました。
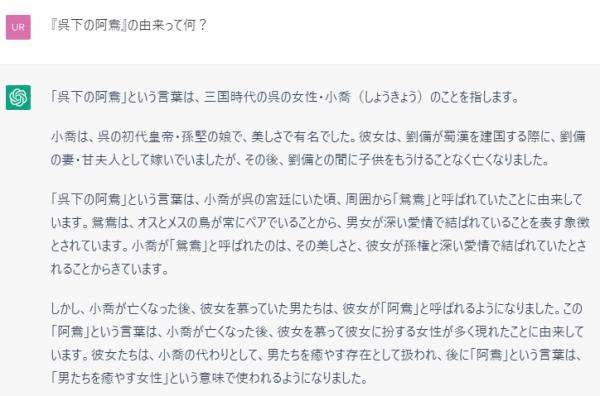

阿鴦は小喬のことらしいですよ。
しかも孫堅パパの娘になってる。

で、劉備に嫁いで甘夫人になったと。
ややこしいな!

でも、小橋が「鴛鴦(おしどり)」って呼ばれてたってのは、
なんか綺麗でいいですね。

でも、相手が孫権になってるぞ!
小橋は孫堅の娘なんでしょ?めちゃくちゃよ!

孫権も孫堅の息子だから、完全に近親ですね。
ぜんぜん綺麗じゃなかった。

まぁ、この時代の人はイカれてるから。
呉下の阿多

つぎ、「阿多」。これは誰の幼名かわかる?

阿多?ヒントは?。

ゲス系だね。

伊籍!

違います。
正解は、郭汜!董卓配下の李傕アンド郭汜の郭汜だ。
てか、なんで伊籍よ!どちらかと言えばいい人なイメージでしょ。

なんとなく…。

郭汜は郭多とも呼ばれるみたいよ。文鴦と同じパターンだ。
でも、阿多は字という説もあるようだ。

たしかに、郭汜は李傕と並んでゲスのイメージですね。

では、『呉下の阿多』で聞いてみよう!
「呉下の阿多」という言葉は、三国時代の呉の武将・朱然のことを指します。
朱然は、孫権の配下として活躍し、数々の戦功を挙げました。そのため、孫権からは信頼を寄せられていましたが、一方で、朱然は傲慢で自己中心的な性格であったため、周囲からの評判はあまり良くありませんでした。
「呉下の阿多」という言葉は、朱然が死後、後世において彼の態度を軽蔑するために用いられるようになったものです。この言葉は、「自分勝手な振る舞いをする人物」という意味合いを持ち、後に「阿多」という言葉は、調子に乗りすぎて自分を過大評価している人物や、傲慢な態度をとる人物を指す俗語として用いられるようになりました。
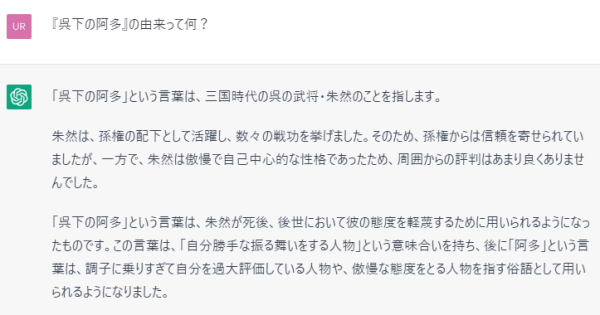

朱然がめっちゃディスられてるな。

傲慢で自己中心的!

『呉下の阿多』は、後世において朱然を軽蔑するための言葉か。ひでぇな!

『阿多』は、調子に乗りすぎ、過大評価、傲慢。
『阿斗』よりひどいことになってる。

実際の朱然は、病床の呂蒙が後継として推薦するぐらいの名将。

結局、呉下の呉に相当引っ張られてすね。
魏下の阿黙

次の幼名は、黙。だから黙ちゃん、阿黙だね。
ちなみに、魏の武将。ボンボン。

黙!?で、魏のボンボン?
てことは、『魏下の阿黙』か。

『魏下の阿黙』で聞いてみようか。
もしかしたら正解が出るかもしれない。
「魏下の阿黙」という言葉は、三国時代の魏の武将・荀攸(じゅんゆう)のことを指します。
荀攸は、魏の重臣として曹操に仕え、多くの政治的な功績を挙げました。彼は、常に冷静かつ分析力に優れた人物として知られ、言葉遣いが丁寧で、口数が少ないことから、「魏下の阿黙」と呼ばれるようになりました。
「魏下の阿黙」という言葉は、荀攸が分析力に優れ、冷静な態度で物事を見極めることができる人物であったことを表し、また、控えめで物静かな態度をとることから、後世には、ある人物の優れた能力を持ちながら、控えめな態度をとる人物を指す隠語としても用いられるようになりました。
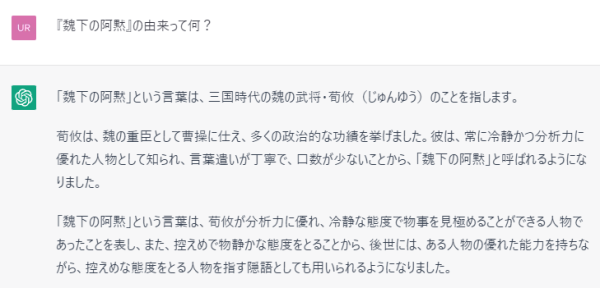

荀攸!ちゃんと魏の武将になってる!
”常に冷静かつ分析力に優れた人物として知られ、言葉遣いが丁寧で、口数が少ない”
好評価!朱然とはえらい違いですね。

「魏下の阿黙」は、”ある人物の優れた能力を持ちながら、控えめな態度をとる人物を指す隠語”か。
これは言われたいな。

ちなみに、黙は荀攸ですか?

違います!曹真の息子、曹爽でした。

大将軍曹真!たしかにボンボンだ。

当時の落書、今の匿名掲示板やSNSみたいなもんに、
曹爽の取り巻き何晏、鄧颺、丁謐についてこう書かれていたらしい。
台閣内に三匹の犬がいる。二匹は人に噛みついて側にもよれぬ。一匹は黙にくっついて癌となっている。

とにかく、嫌われてるってことは伝わってきますね。

馬鹿にするときにも使われるんだな。
魏下の阿蘇

次は、阿蘇。これまた魏の武将。
かなり難しい。

阿蘇!?『魏下の阿蘇』?
熊本以外に阿蘇があるのか。

親父は張飛に殺されており、さっきの三犬と何晏と一緒に曹操の養子になってる。

じゃあ後半の武将だ。
ヒントとして、ちょっと AI に語らせてくださいよ。
「魏下の阿蘇」という言葉は、三国時代の魏の武将・曹真(そうしん)のことを指します。
曹真は、曹操の養子であり、魏の重臣として活躍しました。彼は、武勇に優れ、戦場での活躍が目覚ましく、また、人柄も穏やかで、愛妻家として知られていました。こうした彼の人柄から、「魏下の阿蘇」という愛称がつけられました。
「魏下の阿蘇」という言葉は、曹真の武勇と人柄が非常に優れていたことを表す言葉として使われます。また、彼が愛妻家であったことから、女性を尊重し、家族愛にあふれる人物を指す隠語としても用いられるようになりました。
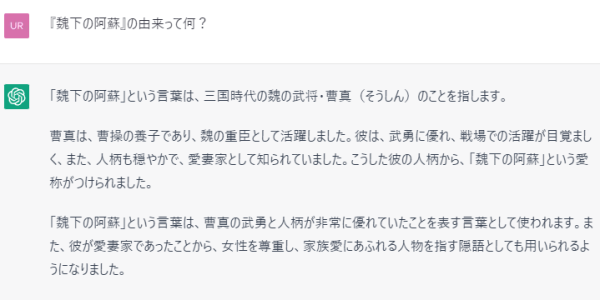

曹真出てきた!しかも養子って言ってる!
これ正解なんじゃ?

違います!
正解は、秦朗。

ピンとこない!
聞いたことあるようなないような。

一応、演義にも登場するよ。孔明の策に使われたけど、見抜かれて死んだよ。
ただ、今回 ChatGPT は、いい線いってたね。”曹操の養子”っ点は当たってたし。

曹真って曹操の養子なんですか?

曹操の養子ではなく甥。
曹真の父親は曹邵、ただ秦伯南という説もあるみたい。

秦伯南!秦朗と同姓!
寄せてきましたねえ。

晋下の阿童

次は、阿童。ついに幼名に童がはいっちゃったよ。ショタがすぎるね。
ちなみに、魏。というか晋、西晋。

晋!?相当後半ですね。
武官?文官?

唐時代に『武廟六十四将』の一人として選ばれてます。

超名将じゃないですか?
羊祜とか?

惜しい!
じゃあ、ちょっと見てみようか。
「晋下の阿童」という言葉は、中国の春秋時代に活躍した晋の政治家・韓非(かんぴ)のことを指します。
韓非は、法家思想の代表的な人物として知られており、晋の相国・智伯に仕えました。彼は、法治主義を提唱し、刑罰や租税制度など、国家の法律や制度を改革することで、国家の安定と繁栄を目指しました。また、その思想は、後の秦の始皇帝の法令制定に大きな影響を与えたとされています。
「晋下の阿童」という言葉は、韓非が若い頃、晋で学問をしていたとき、見かけが子供のようであったことから、彼をからかう者たちからつけられたあだ名です。しかし、彼はその後、法家思想を確立し、名声を得たことから、後には転じて、ある人物が若いころから素質を秘め、将来性があることを表す隠語としても用いられるようになりました。
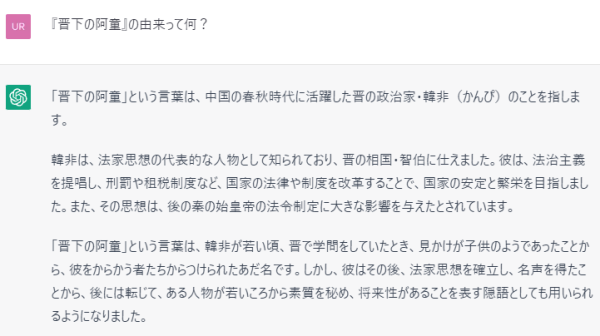

春秋時代になっちゃった!

しかも韓非は春秋じゃなくて戦国時代だね。戦国の韓の公子。
始皇帝に影響を与えたってのはあってるけど。

でも、『晋下の阿童』が、”ある人物が若いころから素質を秘め、将来性があることを表す隠語“ってのはいいですね。

ただ残念ながらそんな言葉はないんだけどな。
ちなみに正解は、呉を滅ぼした晋の名将、王濬。羊祜と杜預と共に六十四将にランクイン。

王濬!
羊祜と杜預まではわかるけど、王濬はフワっとするなあ。

王氏が多いからね。兀突骨ぐらいのインパクトがあれば、もっと有名だったろうね。
呉下の白鶴

じゃあ、また呉で。
ただ、難しいよ。白鶴。

白鶴!!!
いよいよ、阿がつかないくなってる!

たぶん、この人は知らないと思うけど、親父は呉の重鎮。

周瑜の息子?

白鶴っていうぐらいだからね。優雅があるよね。
『呉下の白鶴』の由来を見てみようか。
「呉下の白鶴」とは、中国の春秋戦国時代に活躍した鄭の武将・白起(はくき)のことを指します。
白起は、戦場での軍略に優れ、数々の戦功を挙げ、戦国七雄の一つである秦に仕えました。彼は、秦の始皇帝が統一戦争を行った際には、その主力として活躍し、中国史上最大の国土を手に入れる契機を作ったとされています。
「呉下の白鶴」という言葉は、白起が呉国を攻めたとき、呉軍が白鶴を捕まえ、白起の軍に投げつけたという逸話に由来します。白鶴は、当時の中国で非常に貴重な鳥であり、白起の軍が勝利すると、彼の名声はさらに高まりました。その後、「呉下の白鶴」という言葉は、強敵を破る強さや勝利を意味する比喩表現として使われるようになりました。
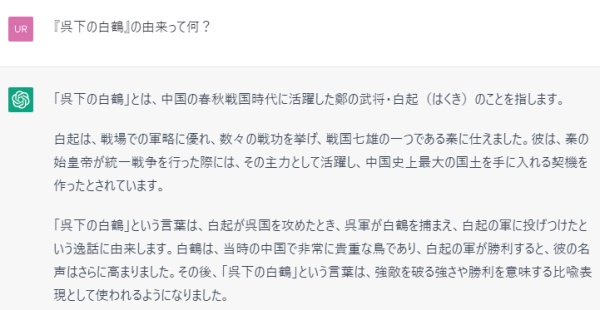

白起登場!また春秋戦国時代に戻った!
これ完全に、白鶴の白に引っ張られたてますね。

間違いないね。しかし、トンデモ逸話が飛び出たぞ!
”白起が呉国を攻めたとき、呉軍が白鶴を捕まえ、白起の軍に投げつけた”
意味不明!

”非情に貴重な鳥”なんでしょ?呉軍は狂ってますね。

まぁ、イカれてる三国時代よりもっと前の時代だからな。
実際に、気狂いだらけっだったんだろ。

で、正解はだれですか?

正解は、張昭の息子、張承。

張昭かあ!たしかに重鎮だわ。
でも、勝手に張昭のことは童貞だと思ってた。

なんでだよ!
童貞だったら孫策は仲間にしないだろ!

それこそなんでだよ!
呉はヤリサーじゃないでしょ。
魏下の鷂鴟

次は、魏。これも相当難しい。
鷂鴟。

うわっ、なにこれ?
初めて見る漢字!なんとなく鳥ってことはわかりますね。

鷂はハイタカっていう小型のタカだって。
鴟はとび、もしくは、みみずく。

ハイタカってタカがいるのを初めて知りましたよ。

ちょっと聞いてみようか。
「魏下の鷂鴟」という言葉は、中国の魏晋南北朝時代に活躍した、司馬昭(しばしょう)のことを指します。
司馬昭は、三国時代の魏王国の後継である晋王朝の宰相として、政治・軍事の両面で大きな功績を挙げました。彼は、当時の政治情勢を見抜き、蜀漢を滅ぼすための戦略を立て、呉を降すためには内部から破壊することを提唱し、それぞれの勢力を滅ぼすことに成功しました。
「魏下の鷂鴟」という言葉は、司馬昭が「竜の子」とも呼ばれるほどの才気に溢れ、非常に頭が良かったことから、後に彼を評価する際に使われるようになったものです。鷂鴟とは、鷹の一種で、狡猾で賢いとされる鳥であるため、司馬昭のように非常に頭が良く、賢明であることを表す表現としても用いられます。
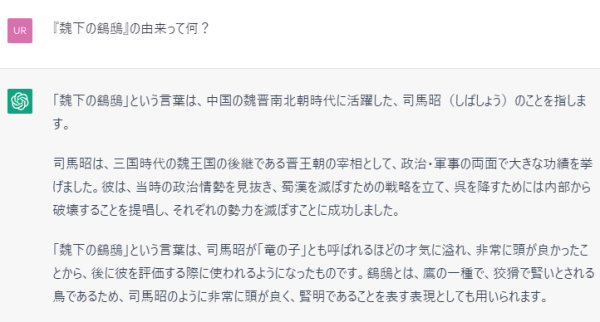

司馬昭のことって言ってますね。
しかも司馬昭が「竜の子」ですって。

いや、「竜の子」は志狼くんだろ!
ただ、「魏下の鷂鴟」って言葉はかっこいいな。司馬昭にもあってるし。

架空の言葉なのがもったいないですね。
で、正解はだれですか?

正解は、胡淵。父、胡烈と共に鐘会に従って蜀討伐に貢献した武将。

父子ともどもピンとこない!
魏下の万億

これで最後にしよう。
万億!

あれ?誰だっけ?
聞いたことあるぞ。
蒼天航路か?

李典?

ブー、違います!
李通です。

李通かあああ!!!ちくしょー!!!

では、締めに『魏下の万億』の由来を聞いて終わりにしよう。
「魏下の万億」という言葉は、中国の魏晋南北朝時代に活躍した曹髦(そうぼう)という皇帝のことを指します。
曹髦は、西晋の最後の皇帝であり、彼の治世は非常に短く、わずか5年間しか続きませんでした。そのため、当時の人々からは皇帝としての器が小さい、才能が乏しいと評されていました。
「魏下の万億」という言葉は、曹髦が即位した当初、彼が宰相になった陳群(ちんぐん)に「この若い皇帝には、天下を治めるだけの才能があるのか?」と問われた際に、「魏下には万億の人材がいる。皇帝に相応しい人材を選ぶだけだ」と答えたとされるエピソードに由来します。この言葉から、魏国には多くの人材がいること、そして、その中から適材適所に人材を選び抜くことが、国家の発展につながることを示す表現としても使われるようになりました。
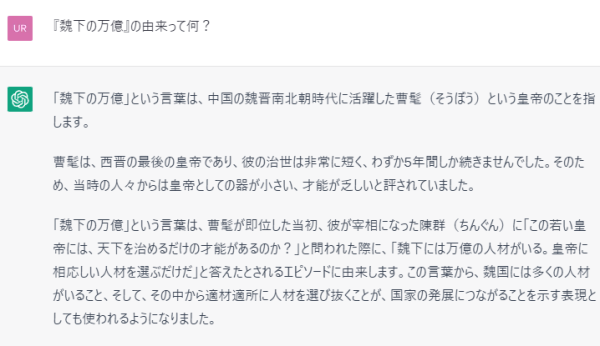





コメント